|
白雪姫になる夢をみた。 せっかくいい気持ちで眠っていたのに、肩をがしっと掴まれてゆっさゆっさと揺らされる。こんな起こし方ってないと思う。 重くて仕方ない瞼をなんとか持ち上げるとそこには見慣れた幼馴染の怒ったような呆れたような顔があった。なんだ。王子様は彦四郎か。もうちょっと捻りがあってもよかろうに。 「やっと起きた」 アクアフレッシュの爽やかなため息が顔にかかる。それくらい近くに顔がある。でも別に驚きはしないし、ドキッともしなかった。それはたとえばわたしの意識がまだ朦朧としているからだとか彦四郎が兄もしくは弟みたいな存在でしかないからだとかそういう理由ではなくて、ただ単にこれがわたしと彦四郎の毎朝の常であるというだけだ。 それにしても王子様のくせに肩を揺すって起こすとはどういうことだろう。ここはセオリー通り甘いくちづけで優しく起こしてくれるべきなんじゃないのか。 「はい起きたらさっさと立つ」 「…ひこしろお」 「駄々こねてもだめ」 甘えた声もぺしっと一蹴される。 まあ彦四郎には無理か。そもそも王子様なんて柄じゃないし。 「枕に抱きつくなよ」 ほら。と伸ばされた右手はきっと、わたしを凄惨な現実にひっぱりあげる不幸の手だ。朝早くに起きて支度をして学校に行って勉学に励まなければならない、義務と通例という鎖が常にわたしをぎゅうぎゅうとしばりつける。でも一度完全に目を覚ましてしまったらたぶん、その後の苦労なんてとるにたらないものでしかなくて、お昼になっておいしい給食を食べれば今日も学校に来てよかったと思うんだろう。人生ってそんなものだ。だからこの骨張って男らしくなった右手が不幸を運んでくるようにみえるのはたぶんまやかしで、本当のところはかみさまの手なのかもしれない。 「お前はほんとに都合がいいんだから」 「今日の給食なにかな、冷凍みかんだったら彦四郎ちょうだいね」 「なんでだよ。僕のみかんは僕のものだろ」 「おまえのものはおれのもの」 「ジャイアンか」 「失礼な、せめてジャイ子と言ってよ」 「ジャイ子でいいのか…」 「知らないの?今ジャイ子はめっちゃ可愛いんだからねあっちゃんなんだからね」 「あっちゃんって誰?友達?」 「これだからもう…」 かみさまもとい彦四郎の手はびっくりするくらいあたたかかった。まるで子供みたい。可愛いなと思ったけれど、言うと怒るのでやめておく。パジャマのボタンをのろのろとはずしながら、昔より随分広くなった背中をぼんやりと眺めた。わたしと違って早朝からしゃきしゃきと動く彼はわたしがぐしゃぐしゃにしたベッドを何も言わずにてきぱきと整えている。お兄ちゃんのようでもあるし、弟のようでもある。綺麗になったベッドをしばし満足げに眺めて、彦四郎がこっちを振り返った。もちろんわたしは着替えをしているので、その様を見た彦四郎はピシッと固まる。そしてみるみる真っ赤になる。可愛いなとまた思ったけれど、やっぱり口にするのはやめておこう。ふふ。憂い奴め。 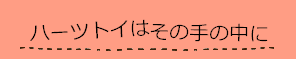 |