|
「まじでふざけんな謙也。あとでしばく」 そんな呪いを込めて転がっていた空き缶を思いっきり蹴飛ばしたら狭い部室の中でカコンカコンと音を立てて跳ね返り見事わたしの脛にクリーンヒットした。カッコーン。金属特有の高い音。くっそ…地味に痛い。やはりこういうことをすると自分に返ってくるものだなあ。体をふたつに折り曲げて、すこしへこんで足元に横たわるそれを拾った。ポカリの空き缶だった。自分で蹴飛ばして自分で拾う、こういうのってなんか惨めだ。 右手で思いきり力をこめて握りしめるとそれはいとも簡単にぐしゃりと潰れた。わーわたしって握力ある。これがスチール缶なら話は別だけれど、アルミ缶なんて目じゃないぜ。潰してから今度はちゃんとゴミ箱に捨てた。フフン、とひとり鼻で笑ってしまうわたしは正直気持ち悪いかもしれない。いや気持ち悪い。しかしそれもこれも全部謙也のせいなのだ。脛の鈍い痛み。ちらかった部室。空き缶。わたしはいきりたっていた。どうして空き缶はあんなにも上手い具合にわたしの脛に直撃したのか。いやそれはもういい。あれは偶然の事故だ。謙也だ。とにかく謙也だ。謙也のせいなのだ。なぜわたしがテニス部の部室にいるのか。そんなこと誰も予想がつかないだろう。わたしだって想像もしていなかった。 (ガチャリ) 「おー!どや、やっとるかー」 「…」 「アレッ元気ないやん。どしたん?」 「アレッじゃないアホ。お前のせいだアホ」 「おまっ2回もアホ言うな!俺はアホちゃう!」 「はっアホでしょめっちゃアホ!謙也のキャッチフレーズじゃん」 「キャッチフレーズがアホて俺どんな人間やねん。ちゃんひどいわあ」 「ひどい!?わたしが!?人に部室の掃除押し付けといて何言ってくれてんのほんと腹立つアホ謙也」 「いやあすまんすまん」 謙也は汗できらりと輝いた顔でわははと笑った。ふざけんなこんにゃろう。治まりかけていた怒りが再びふつふつと湧いてきて右手をギリリと握り締める。こんなことなら空き缶を捨ててしまうんじゃなかった。今すぐ謙也の顔面を殴ってしまいそうだ。しかしもう代わりに潰すものはないし、ペットボトルならそこらへんにいくつか転がっているけどさすがのわたしでも片手でペットボトルは潰せないだろう。だからといって謙也を殴ってしまうのはやはりまずい。謙也はどうでもいい。けれど白石くんに暴力的な女だと思われてしまうのはだめだ。それだけは絶対にいやだ。白石くんはわたしの心のアイドルなのに。 「ええやーん隣の席のよしみやんか」 「よしみって言われてもね…ここまで部室が汚いなんて知らなかったもん」 「ハハッ」 「ハハッじゃないよありえないだろこの汚さ!何が起こったというの四天宝寺テニス部!」 「いやーなんやマネージャーが急にやめてなあ、掃除する奴おらんねん」 「なんでまた急に…」 「白石に告白してふられたらしい」 「うっわ」 「せやろうっわやろ」 「でも石田くんとか掃除しそうじゃん」 「アホかお前もうすぐ全国やで!掃除する暇なんかあったら練習するわ」 「それでわたしが呼ばれたということか…」 「そうやねん☆」 「☆ウッザ!」 部室の散らかり様は本当にひどいものだった。あちこちにテニスボールが転がり(つーかなんで部室にボールが転がってんだ)、脱ぎ散らかした衣服やらタオルやらがおざなりに重なった山がいくつか確認できた。あまりの無残さに思わず目を背けたくなる。フウとため息を吐き、床に座りこんで思う。まったくこれだから男という生きものは。なにやら異臭を放ちそうなその山の中に白石くんのものがないことを祈りつつ頭を抱えた。ウッザてなんやねん傷つくわーとかなんとかぶつぶつ言っている謙也は無視することにする。本当になぜ、なにゆえにわたしがこんな荒んだ部室の掃除をしなければならないのか。謙也か。謙也の隣の席だからか。しかも三年間ずっと同じクラスというオプション付きだからか。そんなことならこんな腐れ縁など今すぐ捨ててしまいたい。仮にこれが白石くんとのものであったならキラッキラした素敵な関係だったろうに。 「緊張して上手くしゃべれないかもしれないなァ…」 「へ?いきなり何?頭おかしくなったん?」 謙也は自分もしゃがむと真剣な表情でわたしのおでこに手を当ててきた。熱ないわアホ。その手をぱしりと振り払う。だいたいコイツには昨日も隣の席のよしみやろーと言われて飲んでいたポカリを奪われたばかりだ。あれまだ一口しか飲んでなかったのに。しかも友達に賭けで勝って奢ってもらったやつだったのに。勝利の末に掴んだ栄光を横取りした罪は重い。そう何度も隣の席のよしみが通用するものか。今度は絶対に断ってやる。決心してぐいっと目線をあげると思ったよりも謙也の顔が近くてびっくりした。目の前で汗がきらりと光った。今日は暑い。謙也も同じくびっくりしたようで、うおっとか言いながら尻餅をついていた。アホだ。わたしは思わぬ近距離にどきどきと早まる鼓動を沈めるためにけらけらと笑った。けらけら。しずまれしずまれ。笑いながら、胸の辺りがぎゅうっとなった。わたしから奪ったポカリを謙也が勢いよく飲み干したあのときと同じ。ぎゅうう。謙也はすばやく立ち上がった。さすがスピードスター。なんだか顔が赤くみえた。 「…あ、お前、あかんで空き缶はここのゴミ箱に捨てられへん」 「ゴミ箱のぞくなアホ。そんなのばれないって」 「お前なあ…ってちょ、これ!」 「は?」 「おま、この缶は捨てたらあかん!横に書いてあるやろ!よく読めや!」 「ええー?あ、ほんとだ。『捨てたらあかーん!』て…アホくさ」 「俺がマッキーでぐりぐり書いてん」 「お前かよ」 「あーあーこんなに潰れてしもうて…」 青いポカリの空き缶の側面には黒い太い線でごちゃごちゃと文字が書かれていた。わたしが潰したせいではっきりとは読み取れないが、なるほど謙也だ。謙也の字だ。汚い。白石くんの字がこんな雑なわけがない。胸のどきどきを沈めるためにわたしはさっきより余計に白石くんのあの素敵な風貌を頭に思い浮かべた。わたしのアイドル。白石くん。謙也ではない。謙也では、ない。 「なんで捨てたらあかーん!なの?」 「お前ばかにしとるやろ…」 「してないしてない。ねえなんで?」 「ええか、これはなあ…」 わたしは黙って聞いていた。その続きを待っていた。その続きこそがわたしの質問への答えのメインの部分だったからだ。しかしいつまで待っても謙也はその先を語ろうとはしなかった。見ると、謙也の口は閉じていた。閉じたというより慌てて塞いだという感じだ。謙也はそのまま手を口に当てて顔面を真っ赤にする。なんだ。なんなんだ。さっきからなんなんだ。つられてわたしまで顔が赤くなっていないか心配になった。なぜならわたしはわかってしまったからだ。きっとアレだ、謙也は、 「…どうでもええやろ」 謙也は、きっとわたしのことが好きなのだ。 |
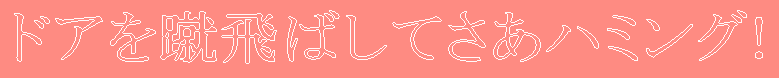
|
ぐしゃりと潰れたそれはわたしが昨日ひとくち飲んだ後に奪われたポカリの缶と同じものだと思った。 これは勘だ。勘だけど、たぶん確かだ。 |
(謙也くんは間接キッスの空き缶をとっておいたというわけです。なんだか気持ち悪い話ですみません。)